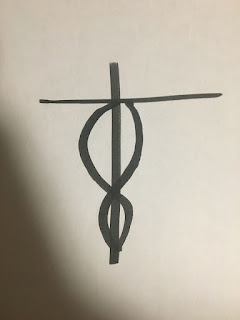"Hotel Room Bed" by Alan_D is licensed under CC BY 2.0 .
作品紹介
CreepypastaであるThe 3:00 AM Mythを訳しました。午前3時は草木も眠る丑三つ時に近い時間ですね。
作品情報
- 原作
- The 3:00 AM Myth (Creepypasta Wiki、oldid=1408664)
- 原著者
- Renigaed
- 翻訳
- 閉途 (Tojito)
- ライセンス
- CC BY-SA 4.0
午前3時の迷信
午前3時は霊が人々と意思を伝えあう時間と考える人がいます。悪魔の印と考える人もいます。午前3時に目が覚めるとき、誰かが自分を見ていると考える人さえもいます。ただ、誰かが見ているとすれば、部屋に窓も扉もないときはどのようにしてこちらを見るのでしょうか。午前3時とはどういうものかということについて、この世には数多くの迷信が存在ます。世界中に存在するこの時間の迷信の本当の意味についてお伝えしましょう。
あなたはぐっすりと眠っていて、夢を見ています。夢を見ている間は、周囲の状況が分かりませんし、クローゼットの中に潜んでいるかもしれない何かにも気付きません。ベッドの下に潜むかもしれない何かにも、掛布団に潜り込んであなたの隣にいるかもしれない何かにも。あなたの目がパッチリと開き、あなたは時間を確認します。腕時計か、携帯電話か、目覚まし時計か、横たわるあなたの周囲にある時間を表示している何かしらで。ただ、時間を知ること自体は本当はどうでもいいことです……よね? あなたは目をこすり、目を数回瞬かせて、部屋の暗闇に目を慣れさせます。
床板が軋む音が耳に入ります。床の上をパタパタという音が走ります。あなたはきっとそれをただの鼠と心の中で思っていますね。たぶん、ただのハツカネズミの類、……いや、ドブネズミの類だろう、と。とても大きな鼠があんな大きな足音をたてているのでしょう。あなたは恐怖で麻痺してしまい、ベッドの端の方を見る勇気が出ません。あなたはただ勝手に怖がっているだけ。こんな馬鹿げたことはもう十分、と自分に言い聞かせます。ただ、それは馬鹿げたことでしょうか。つまり、怖がるべき理由があるのでしょうか。ベッドの下には怪物がいるのでしょうか。あなたが真夜中にトイレに行ったり水を飲んだりしようとして起き上がったところを、怪物が足を捕まえたりベッドの下に引きずり込んだりしようと待ち構えている、ということがあるのでしょうか。
あなたは怪物の存在を信じていません。何年か前の子供の頃に、母親か父親があなたに語ってくれた物語がありました。ブギーマン、サンドマン、その他の怪物の物語は、あなたを怖がらせるためだけのただの物語でしかない……はずですね? ええ、その通り。怪物は実在しない、あなたはそう思い、幼い頃の自分の恐怖心に含み笑いをします。いや、待ってください。あれは何でしょう? パタパタという足音が近付いているようです。非常にゆっくりと扉が開き、キーキーという長く大きな音が聞こえて、あなたはぎゅっと固く目を閉じます。さっき聞こえたのはくすくす笑う声ではないか? いや、もちろん違います。ハツカネズミはくすくすと笑いません。ドブネズミもそうです。あなたは妄想に囚われつつ、ゆっくりと目を開けて、天井をじっと見つめます。
掛布団の下で何かが動いています。被っていると暖かくて心地よい掛布団の、その下で。その何かはゆっくりと曲がりくねりながらあなたの方へ近付いてきます。それはまるで毛布の下で足を引きずっているかのようです。あなたは恐怖で凍りつきます。ここから移動するのは怖い。さもないと、居場所を知られてしまいます。あなたは何かがあなたの着るダブダブの服を引っ張っているように感じます。なんてこと、あれは何? あなたは掛布団を引き上げて床に投げ捨て、目に入ったものにハッと息をのみます。その生き物はいびつでグロテスクであり、あなたのおなかをキリキリとさせます。それは数百年前に織られたかのような破れた布切れを纏っています。それは頭を右に傾け、歪んだ笑みを見せます。その黒くて瞳のない目があなたをじっと見つめます、瞬きもせずに。
あなたはゆっくりと上体を起こし始めて座った姿勢になり、その生き物から後ずさりします。あなたの行動に対しても、それは気に留めていないようです。それはただ、足を引きずりながら徐々に近付いていき、あなたの脚にまで辿り着きます。それはあなたの上によじ登ると、這いより始めます。ゆっくりと、そう、とてもゆっくりと。それは歯を見せてあのゆがんだ笑みを浮かべています。その灰色の肌が骨ばった体からぶら下がっています。その臭いは実に厭らしく、今までに経験したことがありません。ただ、あなたはこの臭いを知っています。今までに嗅いだことがないにも関わらず。その臭いは腐敗臭です。ただ、いかなる腐敗とも違います。腐敗、肉、そして血の臭いが僅かにあります。これからどうしようか。あなたは思案して唇を舐め、目を大きく見開き、その生き物から目を離そうとしません。
それはまだあなたの体の方へ少しずつ動いており、足を引きずりながら進むたびに、徐々にあなたの顔の方へ近付いています。あなたは鼻から深呼吸し、それからとても大きな叫び声を出します。自分の鼓膜が破れたように思います。その生き物は突然に頭を扉の方にぐいと向けて、殺人的な叫び声を漏らします。それは素早くベッドの端の方へ足を引きずって移動し、飛び降りて、ドンと音をたてて床に着地します。急いで扉から出ていき、廊下の暗闇の中へ消えます。
ほらね? 午前3時は小さなものたちが出てきて遊びにくる時間。小さなものたちがその日があなたにとってラッキーな一日かを決定する時間。小さなものたちが姿を現す時間。ただ、思い違いをしてはいけません。小さなものたちを見る機会はほぼ間違いなく最初にして最後になります。安全に逃げおおせたのであれば幸運です。小さなものたちをどう扱うべきか教えることはできません。小さなものたちはどこにでもいるからです。どの家にもいます。あなたの家にあるどの穴にも、どの隅っこにも、どの裂け目にもいます。自分の家にどれだけいるのか、という質問に答えるのは簡単ではありません。教えられることは、小さなものたちはたくさんいるということだけです。小さなものたちはあなたを研究し、あなたを死に追いやろうと企てています。小さなものたちが死の臭いを放つのも不思議ではありませんね。